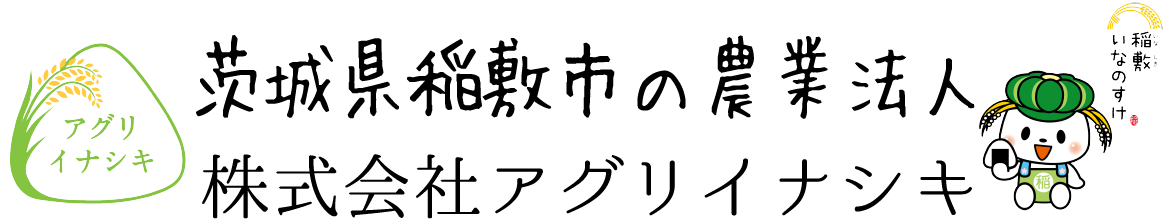1年の集大成が食卓へ
私たちの作るお米に興味を持っていただきありがとうございます。ここではどのような過程を経て、食卓へお米が届くのかを簡単に解説していきます。普段、何気なく食べているお米も、様々な工程を経て皆さんの食卓へ上るのです。

田植えの前に
米作りというと一番初めにイメージされるのは田植えではないでしょうか?
しかし、でこぼこの地面に水を張り苗を植えても美味しいお米は作れません。まずは、田植え前に『代かき』という地面を平らにする作業を行います。この作業を行うことによって、苗がむらなく生育し、田植え作業もやりやすくなります。
『代かき』作業の前には水を張っていない状態の田んぼの土をトラクターで耕す『田起こし』という作業も行い、茨城県稲敷市では田んぼにトラクターが出るようになると春の訪れを感じるようになります。

苗を育てる
田んぼに植える苗を育てます。
緑のじゅうたんのように見える苗は、3月のお彼岸頃に育苗箱に種をまき、来るべき田植えに向けて、育苗器→ハウスと場所を変えながら育てていきます。写真の苗はハウスに移った後ですが、ここからが大変です。4月の気候は変わりやすいので、気温が高い日にはビニールハウスを開け気温を調節し、反対に寒い日にはビニールを閉めきめ細やかな調整を行います。
苗の生育はその後のすべてを決定づけますので、気の抜けない難しい作業です。

田植え
いよいよ田植えのスタートです。
茨城県稲敷市は早場米地帯として知られていますが、例年5月のゴールデンウィーク前後から田植えが始まります。現代では写真のように大型機械の登場で楽になった田植えですが、ハウスから苗箱を取り出す作業は人力です。さらに、田んぼの形によっては手で植える必要のある部分も存在します。
どんなに機械が発達しても人の手や力に頼る部分のあるところが農業のいいところだと弊社では感じています。

稲刈り
5月に植えた苗も順調に成長し、念願の稲刈りを迎えることが出来ました。 例年8月のお盆過ぎから9月末くらいまで稲刈りシーズンが続きます。
実は田植えの後にも、追肥作業(稲の生育状況によって追加で肥料を与える)や除草作業(田んぼの中に稲以外の植物が育ってしまうことを防いだり、田んぼの周りの部分の草を刈る)をする必要があります。さらに、台風との戦いもほぼ毎年起こります。
そんな苦労を経て、やっと迎える稲刈りですから喜びもひとしおです。
そして食卓へ
白いお米にするためには、稲刈りの後にも作業は残っています。
乾燥(収穫したばかりのお米は水分量が多いため、水分量が15%くらいになるまで乾燥させます)
籾すり(乾燥させたお米の表面を覆っているもみ殻を取り除きます。もみを取り除くと玄米になります)
選別(もみ殻などの不要な物を取り除くためふるいにかけます。そして標準以上の大きさの玄米を選び出します)
精米(玄米の胚芽とぬかを削り取り、白米にする作業です)
こうして様々な工程を経てお米は食卓へと上るのです。弊社では白米(精白米)以外に、健康志向の方へ向けた玄米のままの販売も行っております。ぜひ一度弊社の『顔の見えるお米』をご賞味ください。